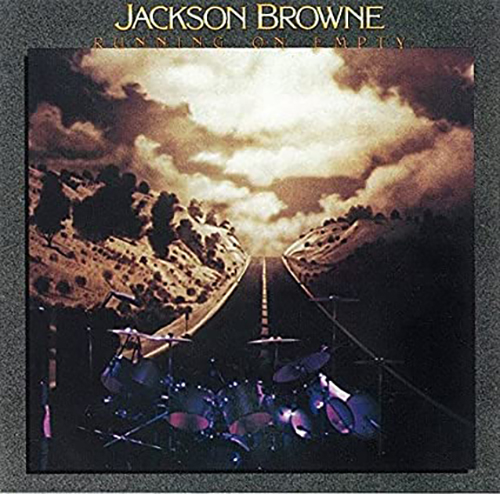ツアーのドキュメントを収めた
ジャクソン・ブラウンの
変則ライヴ盤『孤独なランナー』
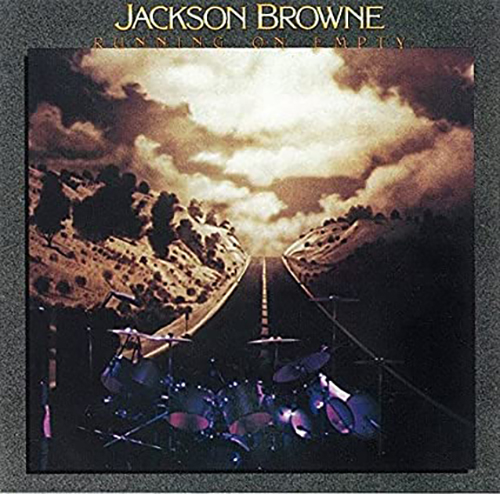
『Running On Empty』(’77)/Jackson Browne
シンガーソングライター系のアーティストが脚光を浴びた70年代初頭、その内省的な作風と繊細そうな風貌から多くのリスナーを惹きつけたのがジャクソン・ブラウンである。彼は新興レーベルのアサイラムから72年にデビュー、3作目の『レイト・フォー・ザ・スカイ』(‘74)は滋味あふれる仕上がりで、完璧とも言えるSSW系サウンドを完成させている。リリースされてから半世紀近くになるが、今でもアルバム全曲、歌詞を見ずに歌える人も少なくないだろう。パンクとAOR/フュージョンが一世を風靡する70年代中頃になっても、彼の作風はデビュー時とさほど変わることはなかったが、ブルース・スプリングスティーンをスターにしたことで知られるジョン・ランドウにプロデュースを任せた4作目の『プリテンダー』(’76)は、豪華なサポートミュージシャンを起用して重厚かつ奥深いサウンドに仕上げている。このアルバムは全米チャートで5位まで上昇、彼のそれまでのキャリアでもっとも成功した作品となった。そして、本作『孤独なランナー(原題:Running On Empty)』は彼の5作目となるアルバムであり、ライヴ盤にもかかわらず全曲新曲ばかりを収録した異色の作品ではあるのだが、『プリテンダー』を上回る好セールスを記録した。
研ぎ澄まされた神聖さを感じるサウンド
先日、アメリカのテレビドラマ(タイトルは失念)を何気なしに観ていると、ブラウンの代表曲のひとつ「ロック・ミー・オン・ザ・ウォーター」がラジオでかかり、それを聴いていた50歳代(と思われる)の女性が自分の20歳代の子どもに「私たちの青春そのものの曲よ」と語りかけていたシーンがあった。ドラマでこの台詞を言わせるということは、当時のアメリカで多くの人に影響を与えたのだろう。「ロック・ミー・オン・ザ・ウォーター」は彼のデビューアルバムに収められておりシングルカットもされているが、チャートでは48位にとどまっている。このシーンを観て、僕はチャート位置と人に与える影響度とは全く別物だということを再認識したのである。ブラウンの音作りには、研ぎ澄まされた純粋さのようなものが感じられるので、リスナーの心に強く残るのだろう。
2ndアルバムの『フォー・エブリマン』(‘73)の中にも、彼が16歳の時に書いた名曲「ジーズ・デイズ」やメドレー仕立ての巧みなアレンジが光る「シング・マイ・ソング・トゥ・ミー」〜「フォー・エブリマン」などに神聖さが滲み出ている。3rdアルバムの『レイト・フォー・ザ・スカイ』(’74)は、少人数のバンドサウンドを中心にしていて、ロックンロールをやっても「レイト・フォー・ザ・スカイ」や「ビフォー・ザ・デリュージ」の神聖な印象が強く感じられ、アルバム全編に重々しい統一感が醸し出されている。リスナーにとっては、その生真面目そうな音楽性が彼の人間性とダブって見え、惹き込まれるのかもしれない。
『プリテンダー』ツアーでの初来日公演
1977年3月、『プリテンダー』のツアーでジャクソン・ブラウンは初来日公演を行なっている。僕は最終日の大阪公演に行った。ツアーメンバーにはデイブ・メイソンの『デイヴ・メイソン・イズ・アライヴ!』(‘73)で最高のキーボードを聴かせていたマーク・ジョーダンや、60年代中頃にラス・カンケルとシングス・トゥ・カムというサイケデリックロックのグループをやっていたベーシストのブライアン・ギャロファロらが来ていたので少し興奮気味であった。コンサート自体は、彼のファンなら誰もが納得できる選曲で演奏も素晴らしかった(特に、デビッド・リンドレーのギターワーク)のだが、ブラウンに関してはライヴを観るよりも個人的にはひとりでレコードを聴くほうが合っていると思った。だから、これ以降は彼のコンサートに行っていない。
余談だが、まだコンサートが始まる前、僕が座っていた席の真ん前に、外国人の女性に連れられた小さいよちよち歩きの男の子がしばらく立っていたのだが、それがのちにブラウンの妻となるリン・スウィーニーと先妻フィリスの息子のイーサンであることはすぐに分かった。アーティストの関係者が普通に客席をうろうろしているのは珍しいことなので、かなり前のことだがはっきりと覚えている。